

平木理平
ライター1994年生まれ、静岡県出身。カルチャー誌の編集部で編集・広告営業として働いた後、フリーランスの編集・ライターとして独立。1994年度生まれの同い年にインタビューするプロジェクト「1994-1995」を個人で行っている。
執筆した記事一覧


イスラム世界への一面的な見方に対する“憤り”が、研究の原動力になる
自らを「落ちこぼれ研究者」と称する、人類学者の鳥山純子さん。かつて「自分はエリートだ」と信じていた彼女の人生は、アメリカ留学での挫折、パレスチナで受けた衝撃、そしてエジプト・カイロでの波瀾万丈な結婚生活を経て、大きく舵を切ることになります。「イスラム教だから」「文化が違うから」——そんな一言で片付けてしまいがちな遠い国の日常が、鳥山さんの言葉を通すと、ぐっと身近に感じられるから不思議です。一体、世界をどんなふうに見ているのでしょう?鳥山さんの波瀾万丈な半生をたどれば、世界の見方が少し変わるかもしれません。
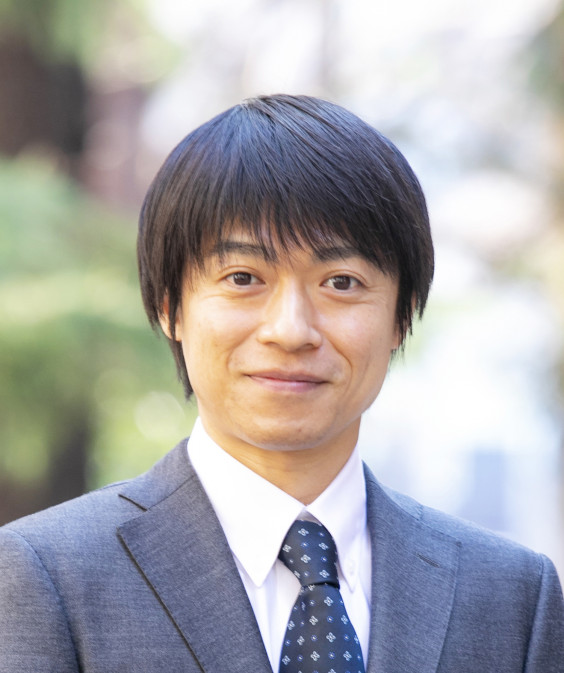
植物と昆虫の驚くべき共生関係から見えてくる、生物多様性の秘密
植物は、自然界の中でただただ“受け身”の存在に見えます。自生している場所から動くことができず、自分の子孫を残すためには、自然現象や虫などといった外的な力に頼る必要があります。人間の目から見ると、受動的な存在にしか思えない生物ですが、しかし植物は我々が考えている以上にしたたかで、能動的な生物のようです。 今回お話を伺った東京大学大学院理学系研究科の川北篤さんは、植物と昆虫の謎に満ちた「共生関係」を探求してきた方です。川北さんのこれまでのキャリアから、植物と昆虫の驚くべき共生関係、そして自身が園長も務めた小石川植物園の取り組みまで、幅広く植物学のおもしろい話を伺いました。

量子の世界にはファンタジーがある。量子コンピューターの進化と共に歩んできた研究者人生
日本の量子コンピューター研究の第一人者として活躍を続ける藤井啓祐さん。GoogleやIBMなど世界のメガ企業が量子コンピューター開発に取り組む現在ですが、藤井さんは量子コンピューターが夢物語として語られていた時代から量子コンピューターを研究してきました。20年以上に及ぶ研究生活を振り返ってもらう中で、藤井さんが見てきた量子コンピューターの進化、そしてどんな未来を見据えているのかをお聞きしました。

人々に深く根付いた「清潔」という価値観はどのように形成されてきたのか
みなさんは毎日風呂に入りますか? 風呂に入らずとも、シャワーなどで毎日欠かさず身体を洗う方も多いと思います。それはつまり、「清潔」な状態でいようと日頃から気をつけているということ。それは「入浴=清潔」があまりにも自明なイメージとなっていることの現れでもあります。そして清潔感とは、現代社会を生きる上で誰しもが無意識のうちに他者に求めるものではないでしょうか。今回話を伺った川端美季さんは、公衆衛生史を専門に、入浴という文化や人々の清潔規範を研究しています。 川端さんは、「本来は身体的価値観であるはずの『清潔』が、近代日本において日本人を統合する国民性として『潔白性』という精神的概念に結びついていった」と言います。人々の常識というものがどのように形成されていくのか、風呂の世界から思いがけない景色が見えてきます。

わずか原子一層分。低次元の世界に広がる物性物理研究の醍醐味を知る
「物性物理」という言葉を聞いたことはありますか? 聞き馴染みのない方が多いかもしれませんが、「物質の成り立ち、構造、現象、機能」などを量子力学や電磁気学を基盤に解明する学問です。物質の性質の起源を研究するこの学問の知見はさまざまな科学技術に応用されており、スマートフォンが動くのも、青色LEDが発明されたのも、リニア新幹線の開発も、すべて物性物理研究の恩恵と言えるのです。 今回お話を伺った高山さんは、物性物理の中でも2次元や1次元といった低次元の領域の物性(※)を専門に研究しています。我々には容易に想像できないミクロな世界の出来事ですが、高山さんのお話を聞いていくうちに、その研究には未知の可能性を自ら切り拓くことができる“研究の醍醐味”があることを感じました。 さらに話は、学生の物理と数学の学び方について広がっていきます。元々は学校の先生を目指し教育学部で学んでいた高山さんだからこその視点で、今の学校の理数教育の問題点が語られています。学生や教育に携わる方々にも、ぜひ読んでもらいたい内容です。 ※:私たちの住む世界は3次元的空間であり、物質もすべて3次元的な広がりを持っているが、物体の端っこである「表面」では、3次元の結晶とは全く異なる性質を持つことがある。近年様々な実験装置の開発が進み、表面に着目した研究が行われたことで、表面では、3次元の結晶とは異なる2次元の周期性をもつこと、表面特有の物理現象が起きることなどがわかってきた。しかし2次元である表面や界面、1次元であるエッジ、0次元のドットなど、低次元系でおこる物理現象にはまだまだ未解明なことがたくさんある。

イノベーションを創出するため、日本のスタートアップ研究には今何が必要か
「スタートアップ」という言葉がもたらす響きは、どこか“光”に満ちています。書店を覗けば、容易に起業家やスタートアップ企業のサクセスストーリーが収められた本が見つかることでしょう。しかし、それはスタートアップに関するごく一部の“光”の面にしか、注目されていないようにも思います。 そこで、イノベーションやアントレプレナーシップ(※)を専門に研究されている加藤雅俊さんに、スタートアップや起業という言葉に潜む実態や問題、そしてイノベーションや経済活性化を巻き起こすには、どんな起業家やそれを取り巻くチーム、支援のあり方が必要だと言えるのか。現在の研究からわかってきたことを伺いました。 ※アントレプレナーシップ:個人あるいはチームが創業機会を発見・活用することで、新しい組織(企業)を設立すること。またはそれに伴うプロセス。


 研究者登録
研究者登録